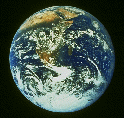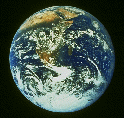私は政治学者ですが、いわゆる「ネオ・マルクス主義」に惹かれて思想形成し、「ポスト・マルキスト」ないし「ラディカル・デモクラート」「自由社会主義者」と自称しています。最近では「エルゴロジー」という「エコロジー」の親戚みたいな思想を提唱しています。昨年インドに滞在して、ますます確信を深めてきました。
私は政治学者ですが、いわゆる「ネオ・マルクス主義」に惹かれて思想形成し、「ポスト・マルキスト」ないし「ラディカル・デモクラート」「自由社会主義者」と自称しています。最近では「エルゴロジー」という「エコロジー」の親戚みたいな思想を提唱しています。昨年インドに滞在して、ますます確信を深めてきました。
以下に、それを解説した三省堂の小冊子『揺れ動く現代への視座』(1997年5月)に寄稿した文章を収録します。私も執筆し、文部省に検定されている、三省堂の高校教科書『現代社会』の宣伝用パンフレットです。
現代とエルゴロジー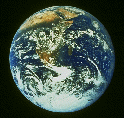
 私たちの生きてきた20世紀は、人類史上未曾有の膨張期であった。1950ー90年の40年間で、世界の人口は25億人から53億人へと2倍に、国内総生産(GDP)の合計は28倍に、輸出は47倍へと拡大した。日本の戦後50年は、そのなかでも突出していた。人口は1・5倍と先進国平均なみであったが、GDPの伸びは円計算で100倍以上、ドル計算では250倍を超える。輸出にいたっては、実に350倍に達する。まぎれもなく日本は、世界史的経済成長の時代の超優等生であった。
私たちの生きてきた20世紀は、人類史上未曾有の膨張期であった。1950ー90年の40年間で、世界の人口は25億人から53億人へと2倍に、国内総生産(GDP)の合計は28倍に、輸出は47倍へと拡大した。日本の戦後50年は、そのなかでも突出していた。人口は1・5倍と先進国平均なみであったが、GDPの伸びは円計算で100倍以上、ドル計算では250倍を超える。輸出にいたっては、実に350倍に達する。まぎれもなく日本は、世界史的経済成長の時代の超優等生であった。
 地球という空間には限りがあるから、それは、人口密度が増し、工業生産物が増大し、核兵器のような破壊力をも集積・拡延し、地球生態系が大きく変化したことを意味した。
地球という空間には限りがあるから、それは、人口密度が増し、工業生産物が増大し、核兵器のような破壊力をも集積・拡延し、地球生態系が大きく変化したことを意味した。
自然との共存、さまざまな歴史や文化をもつ地球人全体の共生が、人類のサバイバルの切実な課題となった。こうした時代をとらえる視角として、エコロジーとエルゴロジーという考え方が重要になってきた。
 エコロジー(Ecology,
生態学)という言葉は、もともとドイツの生物学者で哲学者でもあったエルンスト・ヘッケル(1834ー1919)
が、ダーウィン進化論の影響を受けて、1866年の『有機体の一般形態学』のなかで初めて定義づけたとされる。マルクス『資本論』発刊の直前である。地球生態系危機・環境保護運動と結びついて広まったのは、1970年頃からである。ローマ・クラブ報告『成長の限界』(1972年)などで脚光を浴び、1992年のブラジル国連地球サミットでは、「持続可能な開発(
sustainable
development)」が合い言葉になった。日本でも「エコ・マーク」「エコ・ビジネス」が生まれ、学校教科書にも広く採用されている。
エコロジー(Ecology,
生態学)という言葉は、もともとドイツの生物学者で哲学者でもあったエルンスト・ヘッケル(1834ー1919)
が、ダーウィン進化論の影響を受けて、1866年の『有機体の一般形態学』のなかで初めて定義づけたとされる。マルクス『資本論』発刊の直前である。地球生態系危機・環境保護運動と結びついて広まったのは、1970年頃からである。ローマ・クラブ報告『成長の限界』(1972年)などで脚光を浴び、1992年のブラジル国連地球サミットでは、「持続可能な開発(
sustainable
development)」が合い言葉になった。日本でも「エコ・マーク」「エコ・ビジネス」が生まれ、学校教科書にも広く採用されている。
 現代社会をみるさいに、エコロジーは、重要な視点を与える。自然生態系の重要さと経済成長の限界を警告するのもさることながら、物質的繁栄中心の生活、経済学(エコノミクス)中心の社会科学のあり方にも警鐘を鳴らす。すなわち、人間による自然の改造としての経済活動は無限ではありえず、商品市場経済の「外部」にある資源や土地・水・空気の環境条件を顧慮しなければならない。また、経済学の扱う生産ー流通ー消費では自然と人間との循環は完結しえず、産業廃棄物やゴミの処理も自然と人間とが共存する不可欠の条件である。つまり、エコロジーは、エコノミクス=経済学の存立条件をも、批判的・包括的に扱いうるのである。
現代社会をみるさいに、エコロジーは、重要な視点を与える。自然生態系の重要さと経済成長の限界を警告するのもさることながら、物質的繁栄中心の生活、経済学(エコノミクス)中心の社会科学のあり方にも警鐘を鳴らす。すなわち、人間による自然の改造としての経済活動は無限ではありえず、商品市場経済の「外部」にある資源や土地・水・空気の環境条件を顧慮しなければならない。また、経済学の扱う生産ー流通ー消費では自然と人間との循環は完結しえず、産業廃棄物やゴミの処理も自然と人間とが共存する不可欠の条件である。つまり、エコロジーは、エコノミクス=経済学の存立条件をも、批判的・包括的に扱いうるのである。
 百年前にヘッケルのつくったエコロジーの概念が広まった背景には、第二次世界大戦後の先進工業国での人類史を画する高度経済成長があった。経済成長のなかで伐採された森林、汚れた水、灰色の空があった。日本ではそれが公害とよばれ、経済成長が急速であっただけ自然の変貌も激しく、ミナマタ病やイタイイタイ病は、ヒロシマ・ナガサキと同じように、日本から世界の人々への警告となった。
百年前にヘッケルのつくったエコロジーの概念が広まった背景には、第二次世界大戦後の先進工業国での人類史を画する高度経済成長があった。経済成長のなかで伐採された森林、汚れた水、灰色の空があった。日本ではそれが公害とよばれ、経済成長が急速であっただけ自然の変貌も激しく、ミナマタ病やイタイイタイ病は、ヒロシマ・ナガサキと同じように、日本から世界の人々への警告となった。
 ヘッケルは、エコロジーを自然と動植物の生理的相互関係と位置づけたが、ほかならぬ人間自身も自然の一部であり、動物の一種である。この自然として生物としての人間の生理を、彼はエルゴロジー(Ergology)と名づけた。エコロジーの視点で人間をとらえるとき、自然を制御・征服できたかのごとく語ってきた人間自身の身体的・精神的限界にゆきつく。エコロジーを身体化・主体化した考えが、エルゴロジー(働態学)である。ただしこちらの方は、まだポピュラーではない。
ヘッケルは、エコロジーを自然と動植物の生理的相互関係と位置づけたが、ほかならぬ人間自身も自然の一部であり、動物の一種である。この自然として生物としての人間の生理を、彼はエルゴロジー(Ergology)と名づけた。エコロジーの視点で人間をとらえるとき、自然を制御・征服できたかのごとく語ってきた人間自身の身体的・精神的限界にゆきつく。エコロジーを身体化・主体化した考えが、エルゴロジー(働態学)である。ただしこちらの方は、まだポピュラーではない。
 産業革命によって、それまでの教会や寺の鐘が工場の時計に代わり、自然に合わせた農業のリズムから機械や電気に合わせた工業のリズムが現れると、市場の動きやベルトコンベアーの速さにあわせて、人間身体は変えられていった。「時は金なり」の観念が広まり、時間割やスケジュール管理は、軍隊と学校教育の規律・訓練で浸透していった。
産業革命によって、それまでの教会や寺の鐘が工場の時計に代わり、自然に合わせた農業のリズムから機械や電気に合わせた工業のリズムが現れると、市場の動きやベルトコンベアーの速さにあわせて、人間身体は変えられていった。「時は金なり」の観念が広まり、時間割やスケジュール管理は、軍隊と学校教育の規律・訓練で浸透していった。
 自然から受け継いだ胎内時計(サーカディアン・リズム、睡眠覚醒リズム)により、人間は、夜は眠くなる。ジェット機で海外に出ると、時差ぼけになる。しかし、神経を夜間照明やドリンク剤で刺激し、24時間フル稼働を可能にする交代制勤務が課されるようになった。タイムウォッチを片手に平均作業時間が決められ、作業工程にも分秒単位のノルマが課された。
自然から受け継いだ胎内時計(サーカディアン・リズム、睡眠覚醒リズム)により、人間は、夜は眠くなる。ジェット機で海外に出ると、時差ぼけになる。しかし、神経を夜間照明やドリンク剤で刺激し、24時間フル稼働を可能にする交代制勤務が課されるようになった。タイムウォッチを片手に平均作業時間が決められ、作業工程にも分秒単位のノルマが課された。
 欧米では労働運動の力がこうした動きに対抗し、人間性回復のための労働条件・8時間労働日・休暇制度が整っていったが、遅れて産業化に入り、第二次世界大戦後の半世紀を「欧米に追いつき追い越せ」と駆け抜けてきた日本では、エコノミクスに併せて人間身体を合理化・効率化するエルゴノミクス(Ergonomics、人間工学)が発達し、ついには過労死とよばれる働きすぎの突然死さえ生み出すようになった。
欧米では労働運動の力がこうした動きに対抗し、人間性回復のための労働条件・8時間労働日・休暇制度が整っていったが、遅れて産業化に入り、第二次世界大戦後の半世紀を「欧米に追いつき追い越せ」と駆け抜けてきた日本では、エコノミクスに併せて人間身体を合理化・効率化するエルゴノミクス(Ergonomics、人間工学)が発達し、ついには過労死とよばれる働きすぎの突然死さえ生み出すようになった。
 ヘッケルのもう一つの概念エルゴロジーに、日本の心ある自然科学者・医師・保健学者らが着目したのは1970年頃、ちょうど公害問題が政治的争点になり、環境庁がつくられ、光化学スモッグが工業地帯に蔓延していた時期である。
ヘッケルのもう一つの概念エルゴロジーに、日本の心ある自然科学者・医師・保健学者らが着目したのは1970年頃、ちょうど公害問題が政治的争点になり、環境庁がつくられ、光化学スモッグが工業地帯に蔓延していた時期である。
 公害・環境破壊は、自然を蝕むだけではなかった。超高度成長の過程で、労働災害・職業病や薬害も頻発し、社会問題になっていた。エルゴロジーは、科学者たちがこうした問題にとりくむなかで、日本で形成され発展した。エルゴロジーの言葉自体は戦後日本に導入され、人類学者により「働態」と訳されていたが、1970年に人類働態学研究会(86年に人類働態学会と改称)がつくられ、1972年には英文雑誌『Journal
of Human Ergology』が刊行されている。
公害・環境破壊は、自然を蝕むだけではなかった。超高度成長の過程で、労働災害・職業病や薬害も頻発し、社会問題になっていた。エルゴロジーは、科学者たちがこうした問題にとりくむなかで、日本で形成され発展した。エルゴロジーの言葉自体は戦後日本に導入され、人類学者により「働態」と訳されていたが、1970年に人類働態学研究会(86年に人類働態学会と改称)がつくられ、1972年には英文雑誌『Journal
of Human Ergology』が刊行されている。
 私は、エコロジーとともにエルゴロジーの思想が21世紀の指針にならなければならないと考え、社会科学にもこの視角が導入しようと試みて、『国民国家のエルゴロジー』(平凡社)、『現代日本のリズムとストレス――エルゴロジーの政治学序説』(花伝社)を刊行してきた。より具体的には、いまや英語でもそのまま通用するようになった過労死の問題にとりくむなかで、エルゴロジーを働きすぎ社会日本への警鐘と考えた。過労死を生み出す男性中心の企業社会、サービス残業、そして公共的時間の不足によるデモクラシーの衰退にも、エルゴロジーはヒントを与える。ちょうどエコロジー=生態学がエコノミクス=経済学の存立条件を明らかにし、その限界を照射するように、エルゴロジーは、生産性向上・経済効率に従属した人間工学=エルゴノミクスの限界を示し、人間的自然の回復を基礎づけるのである。
私は、エコロジーとともにエルゴロジーの思想が21世紀の指針にならなければならないと考え、社会科学にもこの視角が導入しようと試みて、『国民国家のエルゴロジー』(平凡社)、『現代日本のリズムとストレス――エルゴロジーの政治学序説』(花伝社)を刊行してきた。より具体的には、いまや英語でもそのまま通用するようになった過労死の問題にとりくむなかで、エルゴロジーを働きすぎ社会日本への警鐘と考えた。過労死を生み出す男性中心の企業社会、サービス残業、そして公共的時間の不足によるデモクラシーの衰退にも、エルゴロジーはヒントを与える。ちょうどエコロジー=生態学がエコノミクス=経済学の存立条件を明らかにし、その限界を照射するように、エルゴロジーは、生産性向上・経済効率に従属した人間工学=エルゴノミクスの限界を示し、人間的自然の回復を基礎づけるのである。
 1950年の日本人の平均寿命は男性58歳、女性61・5歳であった。現代日本の平均寿命は男性76・36歳、女性82・84歳(1995年)、世界一の長寿国で、高齢化社会の到来が言われている。しかし、医療技術がいかに発達し、幼児死亡率が低下しても、寿命がそのまま延びて平均100歳になるわけではない。一人一人の人間にとっては、青春時代や働き盛りの時間を、老境に入って取り戻せるわけではない。ミヒャエル・エンデ『モモ』を参照するまでもなく、日本には会社主義・企業社会という「時間泥棒」がおり、時間は貯蓄できない。ふつうの人々が社会を考え政治に参加する時間は、1日24時間・1年8760時間の限られた枠のなかで、労働時間や睡眠・食事時間を控除した自由時間のなかにある。長時間労働で会社に縛られ、自由時間が乏しいと、家庭も地域社会も政治も貧しくなる。エルゴロジーの視点からみると、現代日本は、ゆとりのない過密スケジュールの国である。
1950年の日本人の平均寿命は男性58歳、女性61・5歳であった。現代日本の平均寿命は男性76・36歳、女性82・84歳(1995年)、世界一の長寿国で、高齢化社会の到来が言われている。しかし、医療技術がいかに発達し、幼児死亡率が低下しても、寿命がそのまま延びて平均100歳になるわけではない。一人一人の人間にとっては、青春時代や働き盛りの時間を、老境に入って取り戻せるわけではない。ミヒャエル・エンデ『モモ』を参照するまでもなく、日本には会社主義・企業社会という「時間泥棒」がおり、時間は貯蓄できない。ふつうの人々が社会を考え政治に参加する時間は、1日24時間・1年8760時間の限られた枠のなかで、労働時間や睡眠・食事時間を控除した自由時間のなかにある。長時間労働で会社に縛られ、自由時間が乏しいと、家庭も地域社会も政治も貧しくなる。エルゴロジーの視点からみると、現代日本は、ゆとりのない過密スケジュールの国である。
 たとえば、こんなデータもある。日本人の17歳男子の平均身長は、1900年に157・9センチメートルだった。それが1994年には170・9センチメートルへと、100年足らずで13センチ伸びた。体重も50・0キログラムから62・9キロへと13キロも増えた。人類学者の観察によると、日本人の祖先である縄文時代の遺跡から発掘された人骨から推定される当時の成人男子の平均身長は、159センチメートルであった。紀元前300年頃に大陸から渡来した面長・高身長のモンゴロイド系弥生人の成人男子平均身長は、163センチであった。その後の日本列島の歴史は、この2つの系譜の混交しあう過程である。だから1876年に来日したドイツの医学者ベルツが1880年頃に測定した男子学生の平均身長は161センチ、なぜかぴったり縄文系と弥生系の平均値になった。その頃の女性の平均初潮年齢は14・7歳、それが百年後の1980年頃には、男子の平均身長は169センチに伸び、女子の平均初潮年齢は12・4歳に低下していた。
たとえば、こんなデータもある。日本人の17歳男子の平均身長は、1900年に157・9センチメートルだった。それが1994年には170・9センチメートルへと、100年足らずで13センチ伸びた。体重も50・0キログラムから62・9キロへと13キロも増えた。人類学者の観察によると、日本人の祖先である縄文時代の遺跡から発掘された人骨から推定される当時の成人男子の平均身長は、159センチメートルであった。紀元前300年頃に大陸から渡来した面長・高身長のモンゴロイド系弥生人の成人男子平均身長は、163センチであった。その後の日本列島の歴史は、この2つの系譜の混交しあう過程である。だから1876年に来日したドイツの医学者ベルツが1880年頃に測定した男子学生の平均身長は161センチ、なぜかぴったり縄文系と弥生系の平均値になった。その頃の女性の平均初潮年齢は14・7歳、それが百年後の1980年頃には、男子の平均身長は169センチに伸び、女子の平均初潮年齢は12・4歳に低下していた。
 より厳密にデータを取ると、江戸時代までほとんど変化のなかった日本の成人男子の平均身長は、明治の殖産興業・富国強兵と共に伸びはじめ、第2次世界戦争期はいったん停滞する。それが、戦後の経済復興・高度成長によって、戦前期より早いテンポで伸びていく。これに伴って、洋服サイズS・M・LのJIS規格も改訂を余儀なくされた。
より厳密にデータを取ると、江戸時代までほとんど変化のなかった日本の成人男子の平均身長は、明治の殖産興業・富国強兵と共に伸びはじめ、第2次世界戦争期はいったん停滞する。それが、戦後の経済復興・高度成長によって、戦前期より早いテンポで伸びていく。これに伴って、洋服サイズS・M・LのJIS規格も改訂を余儀なくされた。
 身長の伸びに作用する要因としては、食糧事情好転による栄養の改善、椅子式生活や体育教育の普及、未成年労働の軽減、ストレスの低下、通婚圏拡大によるヘテローシス(雑種強勢)効果、などが考えられる。確かに1日2食が3食になり、菜食に肉食が加われば、栄養状態は改善されるであろう。だがそれは、本当に健康なのか? 戦後の高度成長は、コメと味噌汁からパンと牛乳へ、ちゃぶ台からテーブルへの移行のみならず、飽食・グルメと膨大なゴミをも生み出した。見方を変えれば、それは、必要栄養量の増大とも、農業労働から工業労働への人間身体の適応とも考えられる。
身長の伸びに作用する要因としては、食糧事情好転による栄養の改善、椅子式生活や体育教育の普及、未成年労働の軽減、ストレスの低下、通婚圏拡大によるヘテローシス(雑種強勢)効果、などが考えられる。確かに1日2食が3食になり、菜食に肉食が加われば、栄養状態は改善されるであろう。だがそれは、本当に健康なのか? 戦後の高度成長は、コメと味噌汁からパンと牛乳へ、ちゃぶ台からテーブルへの移行のみならず、飽食・グルメと膨大なゴミをも生み出した。見方を変えれば、それは、必要栄養量の増大とも、農業労働から工業労働への人間身体の適応とも考えられる。
 たとえば近代日本人の身長の伸びは、座高においてはほとんど変わらない。脚の長さの伸びによる体型変化である。それによって、上半身を支える下半身の骨が弱くなり、こどもの骨折事故が増えたという。下駄から靴への生活変化と幼少児の身体運動量の減少が、足幅を狭くし華奢な脚にしたともいう。田畑や工場での児童労働は消えた。だが、学校教育と塾・予備校での知識修得は、遊びの時間と空間を浸食し、別なかたちで、こどもたちの世界を変貌させた。
たとえば近代日本人の身長の伸びは、座高においてはほとんど変わらない。脚の長さの伸びによる体型変化である。それによって、上半身を支える下半身の骨が弱くなり、こどもの骨折事故が増えたという。下駄から靴への生活変化と幼少児の身体運動量の減少が、足幅を狭くし華奢な脚にしたともいう。田畑や工場での児童労働は消えた。だが、学校教育と塾・予備校での知識修得は、遊びの時間と空間を浸食し、別なかたちで、こどもたちの世界を変貌させた。
 そして実は、日本人成人男子の身長の伸びは、ほぼ限界にきている。1980年代に入ると、伸び率の鈍化傾向が顕著になった。それは、日本より早く工業化に出発したヨーロッパ諸国の身体計測学者が見いだした流れの遅ればせの確認で、日本人の身体の環境への適応が、臨界点に達したことを意味する。だから21世紀に、平均身長2メートルの巨人国が出現することはない。
そして実は、日本人成人男子の身長の伸びは、ほぼ限界にきている。1980年代に入ると、伸び率の鈍化傾向が顕著になった。それは、日本より早く工業化に出発したヨーロッパ諸国の身体計測学者が見いだした流れの遅ればせの確認で、日本人の身体の環境への適応が、臨界点に達したことを意味する。だから21世紀に、平均身長2メートルの巨人国が出現することはない。
 身長の伸びは、一人ひとりの目線を高くした。視野が広くなったといえなくもない。だが、高々10センチの背伸びでは、建物の巨大化には追いつかない。ジェット機が飛び、高層ビルが立ち並び、テレビで世界中の出来事がリアルタイムで放映される。あらゆる情報がビジネスに結びつき、一瞬のうちに映像化されて、まもなく忘れ去られる。そんな景観と生活環境の変化に、心身は必死で適用しようとするが、一人の人生には限りがある。まなざしは高く遠くへ届くようになったが、その視界をさえぎる無数の人工的障害が現れた。情報受容量が膨大になり、それに適応すべく頭脳もひとまわり大きくなったが、情報操作とマインドコントロールの技術も高度化した。科学技術の発展は、学校で修得すべき知識量を増大させてカリキュラムに反映されたが、それはこどもたちの適応能力を超えて、おちこぼれ・不登校やいじめを生み出した。エイズやアトピー性皮膚炎・花粉症ばかりでなく、神経症や心身症など心の病も蔓延した。一言でいえば、日本人の生活空間・イメージ空間は広がったが、その時間的凝集度とストレスは、19世紀までの人々の想像を絶するものになった。
身長の伸びは、一人ひとりの目線を高くした。視野が広くなったといえなくもない。だが、高々10センチの背伸びでは、建物の巨大化には追いつかない。ジェット機が飛び、高層ビルが立ち並び、テレビで世界中の出来事がリアルタイムで放映される。あらゆる情報がビジネスに結びつき、一瞬のうちに映像化されて、まもなく忘れ去られる。そんな景観と生活環境の変化に、心身は必死で適用しようとするが、一人の人生には限りがある。まなざしは高く遠くへ届くようになったが、その視界をさえぎる無数の人工的障害が現れた。情報受容量が膨大になり、それに適応すべく頭脳もひとまわり大きくなったが、情報操作とマインドコントロールの技術も高度化した。科学技術の発展は、学校で修得すべき知識量を増大させてカリキュラムに反映されたが、それはこどもたちの適応能力を超えて、おちこぼれ・不登校やいじめを生み出した。エイズやアトピー性皮膚炎・花粉症ばかりでなく、神経症や心身症など心の病も蔓延した。一言でいえば、日本人の生活空間・イメージ空間は広がったが、その時間的凝集度とストレスは、19世紀までの人々の想像を絶するものになった。
 このストレスフルな時代に、エコロジーの視角から自然環境を回復するとともに、エルゴロジーの視点から心身機能をも回復することが、現代の重要な課題となっている。
このストレスフルな時代に、エコロジーの視角から自然環境を回復するとともに、エルゴロジーの視点から心身機能をも回復することが、現代の重要な課題となっている。
 20世紀が終わり、21世紀に入ろうとしている。日本型経済成長はアジア地域に広まり、公害も過労死もグローバル化している。20世紀前半の世界戦争は人類史上未曾有の環境破壊であったが、後半の多国籍企業中心の世界経済も人間のあり方を大きく変貌させた。21世紀を目前にして、エコロジーとエルゴロジーをベースに、かけがえのない地球と私たちのいのちを、サバイバルさせなければならない。
20世紀が終わり、21世紀に入ろうとしている。日本型経済成長はアジア地域に広まり、公害も過労死もグローバル化している。20世紀前半の世界戦争は人類史上未曾有の環境破壊であったが、後半の多国籍企業中心の世界経済も人間のあり方を大きく変貌させた。21世紀を目前にして、エコロジーとエルゴロジーをベースに、かけがえのない地球と私たちのいのちを、サバイバルさせなければならない。

研究室に戻る
ホームページに戻る